9月末、連続5日間の休暇が取れる・・・ そう知った僕は、きみに会いに行く決心をした。
そう、40 年前に、きみと見た なつかしい風景に、会いたくて。
今、どうしても・・・ 会いたくて。

きみは輝ける空の下、碧く、静かに佇んでた。
関越トンネルを抜けて見た越後湯沢の風景は、土砂降りの二乗くらいの雨の中に霞んでた。
フルワイパーにしても、前なんか、まるで見えない。
幸い、平日で交通量が少なかったので減速し、安心して走れる速度をキープする。
後続車がいたらビビリな僕は、無理しても速度を維持しただろうけれど。
バックミラーにも、ドアミラーにも、後続車は写らない。
( よかった・・・ )
長岡へ近づくに連れ、雲は高くなり、所々に切れ間も見えた。
左手側の北陸道方面の空は、さらに明るい。
40 年前に後にして以来、3日間といたことのない場所。
そこを「ふるさと」と呼ぶ資格なんて、僕にはあるのだろうか・・・
母さん・・・
ずっと、心配ばかりかけた、けど・・・
ごめんね。
僕は、どうしても、あの頂に立ちたいんだ。
理由は言葉にしなくても、母さんは知ってるはずさ。
言い出したらきかない子だから・・・って、
いつも、そう言って、でもいちばんに、僕を信じてくれた、母さん。
もし、そこに「リアルな」 プーさん がいても・・・
僕は、頑張って、逃げる、から。
必ず、元気で、帰るからね。
母さん・・・
スタートは海抜0m
きみに再び登ると、そう、決心した時から僕は決めていたんだ。
スタートは、海抜0m。
それだけは、絶対に譲れない。
日本海の「水」に触れて、そこから垂直方向へ 992 m、
水平方向での移動距離は概算 6.7km くらいか?
そこに、君の頂きがある。
2025年10月3日、午前6時。
「きをつけていきなせ」
母さんは、いつも通りの笑顔と、言葉で、僕を送り出してくれた。
僕的な予定では、きみの頂きにあるはずの避難小屋に泊まって、
ふるさとの街の夜景を、じっくり見たかったのだけれど、
母さんの顔を見たら、さすがにそれは言い出せなかった。
僕のいちばんの目的は、きみの頂きに立つこと。
ふるさとの街の夜景を見るのは、その先の未来でもかまわない。
だから、僕は母さんに約束した。
米山駅発16時48分の電車に乗って、必ず、帰るからね。と・・・
海岸通りの無料駐車場にクルマを停めた。

時刻は午前6時15分。柏崎駅までここから1kmちょっと。
歩いて駅へ。
真水は 1.5 L ザックに用意したけれど、それとは別にペットボトル飲料を何本か持ちたい。
駐車場から駅までにコンビニか、自販機があるだろう・・・そう思いつつ歩くが、それがない。
どうしようかと悩みつつ、駅に到着してしまった。

駅のコンビニで、おにぎり1個と、ペットボトル飲料を購入。
兼非常用食料として太平洋側から持参した「乾きもの」系のごく軽量な食べ物と合わせて2日分。
これで日帰り予定の食料に心配はない。
米山駅までの切符を購入。運賃は 240 円。
米山駅は無人駅と聞いたので現金を券売機に投入する。
Suica にチャージしたお金があっても、僕のふるさとでは、それはまだ忘れるべきことのようだ。
券売機を前にして、たまらなく、うれしい 気持ちがしたのは、なぜだろう・・・

普段使いではない、登山用に愛用している時計を、見る。

40 年前、おそらく、これに近い時間。
僕は、この駅から、同じように、この電車に乗車した・・・ はずだ。
なつかしい、ともだち といっしょに。
でも、なぜ、だろう。
どうしても、その時のことを、思い出せない。
なぜ、なんだろう・・・
あぁ 電車が、動き、始めた・・・
鯨波、青海川、笠島・・・ なつかしい駅名をアナウンスする声が聞こえる。
車掌さん、乗車中のみなさんにとっての日常は、今日の僕にとっては特別な時間だ。
ただ、特別な時間でありながら、米山駅の風景を、僕はどうしても思い出せなかった。
駅の風景すら、思い出せないままの僕を乗せて・・・
やがて電車は、記憶にない、でも、なつかしいはずの駅へ 着いた。

きみの真横(西側)?へ来た。
かすかに、きみの横顔が見えた。

山を登りに来た。それは、間違いのない事実だが。
でも、僕は、海を目指す。
スタートは、海抜0m。
そう、決めて いた から。
振り返れば、波 静かな・・・ ふるさとの海が・・・

水平線の向こうに沈む太陽を、僕は何度、数えたかな・・・
感傷に浸りながら、左右を見回して、海への道を探す。
もとより僕は、米山駅付近の海岸へ通じる道を知らない。
( ほぼ海岸にある駅だ。海なんて、すぐ、行けるだろう・・・ )
そう思っていた自分の考えの甘さにすぐ気づき、取りあえず、唖然とする。
( 海岸線に沿って線路があるってコトは、踏切を渡らないと、海へは 絶対に行けない!)
でも、米山駅の左右、どっちを見ても、見渡す限り、およそ踏切なんて、『 ない!』
叢に一箇所、「強行突破用の小径?」に見える「何モノかの踏み分け跡」があったが。
もちろん、そんなところは、通れても、通れない。
現在時刻は7時30分。
登山口のある大平集落までは、米山駅から約 4.2 km。徒歩で約1時間。
午前9時に登山を開始するなら、あと 30 分以内に大平へ向かわねばならない。
復路を思うと、ここから海まで、行って 15 分がリミット。
海に向かって考える。右か、左か。
わからん。
でも、人家は海に向かって右側の方が、圧倒的に多そうだ。
ってコトは、僕の実家もそうだけど、人々の生活は海に密着してるはずだから、
海に向かって右側の集落のどこかに、海岸の砂浜へ通じる道が「必ず」ある、はず。
そう信じて、駅から海に向かって右手側の集落へと続く国道8号線沿いの道をひたすら歩く。
5分もしないうちに汗が流れ落ちる。
なんでだ? 着てるのは F社製の速乾 Tシャツ1枚だけだぞ。
今日は10月3日、まだ午前7時30分、秋分はもう10日も前に過ぎただろ?
どうして、こんなに暑いんだ?
記憶は時を駆けて・・・ 遠い 過去へ
でも、あの時も暑かったよな・・・
やっぱり、40年前の4月1日、僕はオンボロのチャリンコに乗って・・・
この道を・・・国道8号線を、京都へ、その先へ
延べ 1000 km の道を 夢中で駆ける旅に出たんだ・・・
若かった 夢のせいかも しれないけれど。
あの時も、僕は冷たい風の中、汗が流れるのを感じてた・・・
そう思った途端、時は過去から現在に舞い戻る。
そうだ。40 年経っても、僕は、何にも・・・ 変わって ない じゃないか・・・
うん、やっぱり僕は、僕でしか、ない んだ。
歩き方は、変わらない。
違う。変えられないんだ。
歩き方も・・・ 何もかも、全部。
僕は・・・初めから、僕で、最後まで、僕でいるしか、ない から。
それを確かめたくて、今日、ここに来た。
ちがうかい?
そう思いつつ、きっと、あるはずの標識を探す。
それは・・・
『 米山海水浴場 → 』
あった! この表示を待ってたんだ。
重いザックを背負って、気持ちだけは駆けるように急ぐ。
見えた。集落の外れで、道が「線路の上を越してる!」
集落の外れは「海食崖」で、トンネルがあり、その手前で、
道はトンネルの上を越して、小さな海水浴場へと続いていた・・・

法的な基準は違っていても構わない。
僕の海抜0mは、ここなんだ。
どうしても、ここから、始めたかったんだ。
きみへの旅の始点。
それが、ここさ。

僕は、きみの頂きへ、行く。
きみは、おそらく、誰をも待たず、また、誰をも追わないだろう。
でも、人は、誰かを待ち、誰かを追い、時にはそれに疲れ、俯いて、
そして、僕のように、きみの頂きを目指すこともあるだろう。
僕は、知っている。
きみは、黙して、何も言わない。
救いなど、ない のだ。
きみも、知っている。
救いなど、ない ことを。
ならば、きみの頂で
せめて 共有しようじゃないか。
きみが 1500 万年間 見てきたであろう 風景 を・・・
大平への道

予想以上に時間をロスしたが、大平登山口午前9時の予定には何とか間に合いそうだ。
ただ、ここから大平までの道が皆目わからない。
道は覚えていないが、Google Map という、40 年前にはなかった Secret Weapon も、今はある。
それに頼らなくても、米山駅の近くには、大平登山口への道を案内する標識があった。
あそこまで戻れば、なんとかなる、はずだ。

かつて、ここを歩いたことは、もちろん記憶にない。が、40 年前、8号線も、北陸道も、すでに存在していたのは間違いない事実。ただ、なんとなくあの頃は、国道8号線を横断していたような・・・ かすかな記憶があるような気がするが、それは思い違いか・・・?
案内標識の矢印方向を見ると・・・

記憶にない風景には、やはり違和感を感じてしまう・・・
迷っている場合ではない。
9時までには大平登山口へ行かねばならない。案内標識を信じてガード下をくぐる。
その先に見えた道は・・・

ここを、何度、歩いたんだろう。
少なくとも何往復かはしていると思うのだが、断片的な記憶しかない。
はっきり、覚えているのは、正直1度、それも往路だけだ。
あの時、歩きながらチーズの話をしてくれた人は、確か、高校の体育の先生だったはずだ。
お名前も、お顔も、もう、思い出せないが・・・ 確か、黒縁の眼鏡をかけていたような・・・
唯一、間違いないと思えるのは、年齢だ。
あの時、先生は、今の僕とそう変わらない年齢だったんじゃないか?
いや、もっと、若かったかもしれない。
僕の思い込みも、多分にありそうだからな・・・
今でも、お元気でいらっしゃるだろうか・・・
その想いをきっかけに、まるで、泉が湧き出だすように、僕の中に記憶がよみがえる・・・
そうだ、思い出した。高校2年の2月10日も、僕はここを歩いたはずだ。
あいつとふたりで頂きを目指した日、僕は間違いなくこの道を歩いている。
雪庇とクレバスと、吹雪の中、やっとたどり着いた雪に埋もれた山頂の避難小屋、
寒かった吹雪の夜、朝、強風の中でバリバリに凍った手袋等の断片的な記憶。
その中に下山後の復路の起点、大平付近?と思しき風景が残っている。
記憶は断片的でも、あの時、米山駅-大平間を歩いて往復したのは間違いない事実だ。
だから、記憶に残る回数で言えば、僕がこの道を歩くのは3回目ということか。
実際には、何度、歩いたのだろう・・・ その数倍はあると思うのだが。
確かめる術もなく、今さら、確かめたところで何かがよみがえるわけでもないが・・・
40 年の歳月は、こんなにも過去を風化させてしまうものなのか。
あらためて、過ぎ去った日々の事どもを思う。

山頂方向には、うすい雲があるが、海側はよく晴れている。
予報では、今日は上空に薄雲の広がりやすい晴れだと言っていたが、雲はどちらへ動く?
振り返れば・・・、ずいぶんと遠く、下の方に海が見える。
もう 100m くらい登ったかな?

時計で高度を確認。
当てになるような、ならないような・・・

まだ、大平へ着かない。
少し、遅れている?
トレッキングポールにぶら下げた『クマよけの鈴』の音が盛大に響く。

でも、心から、ありがとう。
だんだん、明るくなってきた。

時間的には、もう大平へ到着してもいい頃だ。
そう思いつつ、コーナーを曲がると・・・ 何軒か、家屋が見えた。

時刻は、午前 9 時 7 分 58 秒、予定より若干遅れている。

ここで、想像もしていなかったモノを発見!

自販機の脇には・・・

2025年 10 月現在、大平の米山登山口駐車場は改修工事中で使用できないという事前に得ていた情報の通り、上の画像のすぐ右側では重機を入れての工事が進められていました。ヒザまで泥に浸かって、作業している皆さんに頭を下げて先へ進みます・・・

この「舗装されてる道」、記憶にあるカモ!
そう感じつつ、先へ進むと、

こんな感じの斜面の小径を、ちょっと登ったら、また道幅の広い林道に出て

案内標識があった!

2時間30分という意味なのだろう。
そうだ。なんとなく・・・ ここは覚えてる!
左へ行けば林道。標識の右側(写真では正面)の小径が登山道だ。
昨日の激しかった雷雨の名残りか、道はかなりぬかるんでいるようだ。
今日行くのは、木の根っこと、泥んこの道?
森林限界より上の世界が好きな僕は、ちょっとため息。
でも、それは想定内。
林道の方が歩きやすい? のかもしれないが、ここはもちろん「登山道」方向へ。
なんせ 40 年振りの道。この先のことを考え、念のため地図も確認。

「偏差値 25 m」とあるから、誤差の範囲内なのだろう。
大丈夫。これならひとりでも道に迷うことはなさそうだ。
行くぞ!
輝かな 風景
いつものトレッキングポールに助けてもらい、一歩一歩、確実に大地を踏みしめて登って行く。
おぼろげながらも記憶にある通り、やはり、この山の登りはきつい。
実際、平均しての傾斜角はどれくらいになるのだろう?
今日は、純粋に海水に触れてからスタートしているから、登りの標高差は米山の高さそのもの、最新のデータでは 992.5 m だ。で、水平方向の移動距離は、出発地点の米山海岸から米山山頂まで、3500 ~ 4000 m 程度のようだ(米山海岸は、おおよそ北緯 37.32 度、東経 138.52 度付近、米山山頂は、北緯 37.2895 度、東経 138.4839 度。地図上で両地点を結ぶ直線を測定すると、約 3.7 km前後の水平距離になる。実際には、斜面を登るために移動距離はより長くなり、登山ルート全体では約 5.5 〜 6.0 kmほどか?)。これを元に平均傾斜角を求めると、14 ~ 15.8 度くらいになる。これは登山道や坂道として快適な歩行の限界とされる 6 ~ 10 度をはるかに上回る値だ。
てか、計算するまでもなく、この登攀は、当たり前に、苦しい。それが、真実。
トレッキングポールなしでは、到底、僕には登れない。
はぁ はぁ はぁ
ふと気づけば、登山道一面に大量の栗が落ちている・・・

あわわ・・・
必死で歩く速度を上げようとするが、足が前に出ない。
恐怖心もあるが、登りが急傾斜すぎて、既に、体力の限界なのだ。
それでも、よろめくように、必死に前に出る。
今にも藪からクマが栗を、いや僕を、食べに現れそうな気がして、たまらない気持ちになる。
しかし、登りが・・・ 僕には急すぎる・・・ これ以上は、マジ、ムリ。
はぁ はぁ はぁ きつーい。
心臓が口から飛び出しそうだ。
やばい。こんなハイペースでは絶対に参ってしまう。
少し、休まなければ・・・
そう思って、振り返ったら・・・

あそこから、来たんだ・・・
心象風景と、現実風景のあまりの違いに、
心象風景のクマのことは忘れ、我に返って、しばし、現実の風景を見つめる。
さっきまで、あそこにいたんだよなー
なのに、もう、ここまでこれた。
あと残り、2/3くらいかな?
タオルはもう、吸水力の限界。でも、替えのタオルは持ってこなかった。大失敗。
ザックのハーネスに付けたペットボトル飲料の残りも、あとほんの少ししかない・・・
( 大平の自販機で2本買ってきてほんとによかった! ただ、むちゃ、重たいケド )
そう思いつつ、ペットボトルに残った飲料を心置きなく飲み干して、替えのボトルをザックのポケットから出し、空になったボトルと交換する。これでペットボトル飲料は残りあと3本、水は昼食用に 500 mL、予備の水筒に1L残っている。ここまで発汗がすごいと、飲料水は、その重さより、やはり量が優先する。もちろん、山頂から 15 分ほど下ったところに水場があることは今でも記憶にある。が、たとえ、それを覚えていても、今、ここにある水が愛しい。ヒトには水に対する言葉にできない欲求があることを、僕は山に来るたびに感じてしまう。
( そうだ。熱中症対策もしておこう・・・ )
持参した・・・ と言うか、正確には、前回の山行の残りの塩あめをザックのポケットから取り出して、口に含み塩分もチャージする。ここで熱中症になったら助けてくれる人は誰もいない。クマの件も含めて、ここでのことはすべて「自己責任」。それがきみと僕との絶対に守らねばならない約束だ。
それにしても、発汗がひどい。夏の山行以来、運動していなかったこともあるが、この時期にしては気温が高すぎるんじゃないか?
このすぐ先、標高 650 m 付近に「二ノ字」という少し開けた場所があったはずだ。
そこで少し長めに休憩しよう。
そう思いつつ、登山道を 見上げる・・・
そう、『見上げ』る。
なんだか、おかしな表現だが、この場合、そう表現するのが最適なのだ。

作って下さった方に、心から感謝。
階段を上る際、通常は右足と左足を交互に前に出す。でも、ここではそれが出来ない。階段一段分の幅が広いこともあるが、それより何より、かなりの急登による疲労の蓄積のためだ。ヒザはガクガク、大腿はヒクヒク、どちらにも「ちから」というものが感じられない。基礎体力の衰えををあらためて実感。
毎日、ウォーキングしていた頃のふくらはぎのハリが、今はない・・・
( 仕事でも登らなければならないんだ。運動しなきゃ! )
ただ・・・ その思いを、今、暮らしている街まで、持ち帰れるか・どうか、それが問題だ。
そんなとりとめもないことを思いつつ、整備された階段を上り続ける。
はぁ はぁ はぁ 太腿の筋肉が限界だ。
「二ノ字」は・・・ まだか?
一歩、足を踏み出す度に、その思いだけを噛みしめる・・・
何度、何回、その思いを繰り返した ことか。
フッと視界が開けたと思ったら、そこが「二ノ字」だった。

米山(米山駅から往復)
URL:https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-719251.html より引用
ここの標高は、約 650 m 。
山頂が 992.5 m なので、およそ全体の 2/3 を登ったことになる。
ここからは、きみの てっぺん が見えた。
手をのばせば届きそうとは言わないが、もうすぐそこだ。

きみの てっぺん を見つめて呼吸すること、しばし。
さっきまで、肩で息をしていたことがウソのよう・・・
きみに、本気で会いたくなった 時から
こんな きみの姿に、会えると ずっと 信じてたんだ・・・
僕は、なぜ、きみに会いたくなったんだろう・・・
僕は、どうして、ここへ、来たんだろう・・・
きみの てっぺん に向かったまま、僕自身に、問いかける・・・
きみを見つめている 僕は・・・
40 年前の僕と・・・ どれほど変わったのだろう?
きみは、変わってなかった ね。
うん。僕も 変われなかったんだ。
それを、確かめに、ここへ 来た。
変わらないきみに会えたら、決して変わらないものもあるんだと・・・
もしかしたら、そう思えるんじゃないかって、僕は思ったのかもしれない。
僕の周囲では、瞬く間に変わってしまうことの方が、あまりにも 多すぎた・・・ から。
では、変わらなかった もの って、何?
それを、きみに、問いたくて。
そして、分かち 合いたく て・・・
「二ノ字」の真ん中にある岩に預けていた僕のザックのハーネスを握る。汗を吸い込んだハーネスは風に吹かれて驚くほど冷たい。日帰りなので、それほど重たいわけではないが・・・ この冷たさは格別だ。
うん。じゅうぶん、休息した。
歩く気力がよみがえってきた。
ザックの左ハーネスを左手で持ち上げ、僕の左肩に通して体を時計回りに回転させる。
続けて右手をザックの右ハーネスに通し、軽くジャンプしてザックのフィット感を確かめる。
見上げれば、きみと同じく、僕も・・・
今、輝かな空の下。
陽の当らないところを歩むことが多い僕には、もったいないくらいの明るさだ。
711米峰

あぁ もしかして、あの場所は・・・
12 歳の時に見た、生涯、忘れないであろう風景が見えた場所?

間違いない。きっと、ここだ。
12 歳だった僕は、あの日、ここから妙高山と火打山と焼山を見た。
そして、その向こう側には、さらに高く、真白な雪を被った北アルプスの山々が見えたんだ。
きみより高い山を見たことがなかった僕にとって、きみの向こう側に、きみより高い山があることは想像を絶する驚きだった。
純粋に、憧れた。
登ってみたいと、心から思った。
そうだ。あの日、息をのんで、見つめていた 風景だ。
新潟県柏崎市周辺では、12歳(小学校高学年)になると、地域の大人とともに米山に登るという風習がかつてあった。
登山を通じて自然の厳しさや美しさを体験し、地域の信仰や歴史に触れる良い機会でもあったようだ。
やがて、高校生になった僕は、これが原体験となって、迷うことなく山岳部へ入部した。

その名前からわかる通り、ここの標高は 711 m

米山海岸で高度 0 mに設定した高度計の示度は、真の標高より 16 mほど低い。これは、上空にあった薄雲がとれてきた(=気圧が上がり、天候が良くなった)ためか?
地形図は、ここから先はしばらくハイキングコースのような道が続くことを示している。
でも、確かこのあたりに、急勾配の斜面をトラバースする、ちょっと危険な場所があった・・・はずだ。
traverse(横断する、横切る):登山で使われる場合は、「急斜面や崖のような場所で、上下ではなく横方向に移動すること」を意味する。
あの急斜面は、どこだろう?
ブナ林とガンバレ岩

もう、避難小屋がはっきり見える。
711米峰を過ぎてからは、ハイキングコースとまでは行かないけれど、少し下るような場所もあって、中盤、中休み的な道を進む。しかし、稜線の上のような両側が切り立った崖になっている箇所もあり、体力的には楽でも、気は抜けない。万一、滑落したら、助けてくれる人はいないのだ。携帯電話の電波も先ほど調べたら、僕のは圏外だった。
( 集中! 集中!! )
しばし、慎重に進むと見えてきたのは・・・
あぁ ブナ林だ・・・

高度 700 m から 800 m 付近にかけて、見事なブナ林が広がっているのも昔のままだ。
あのころは、ブナの根を掴んでよじのぼっていたような記憶もあるのだが・・・
傾斜もまたきつくなってきた。肩で息をしながら、ブナ林を上へ、上へ、進む。
そして、またひとつ、なつかしいものに出会えた・・・
あぁ ガンバレ岩だ!


昔は、こんなに、くっきり・はっきり 描かれていなかった・・・? ような覚えがあるし、手前にはハシゴはまだなくて、木の根っこを掴んで、服をドロで汚しながら這い上がった?ような気がするのだが、気のせいだろうか・・・
ちょっと待って・・・
急斜面のトラバースはどこへ行った?
たしか、ガンバレ岩の手前だった気がするが・・・
もしかして、危ないから、ルートが変更されたんだろうか・・・
もし、そうだとしてもまったく気づかなかった!
・・・ってか、さっき稜線みたいだなって思いながら通過したところがあったけど、両側が切り立った崖のように感じたぞ。むかしはあんな場所はなかった気がする・・・。もしかして、あれが新しいルートだったのかな?
尸羅場? 高校生だった当時の記憶にはない場所だ。
なんと読むのだろう? そして、なにをした場所なんだろう?

木の枝に付けられた表示によれば、尸羅場とは「ここより先は女人禁制(女性の登山禁止)とされていたかつての結界」なのだそうだ。奥にはお地蔵さんもいらっしゃっる・・・ かつて、ここまで、大切に、大切に担ぎ上げた方がいたのだ。この事実ひとつを見ても、昔の人々の山への思い(信仰)が伝わってくる。一礼して通過する。
水場
40年前、登山で水を運ぶ(入れる)モノと言えば、間違いなくそれは「ポリタンク」だった気がする。正確には、本体がポリエチレン(PE)製でキャップがポリプロピレン(PP)製の水容器だが・・・ 特に多く使われたのは耐衝撃性・耐薬品性に優れる高密度ポリエチレン(HDPE)で、今思えば、なんとも言えない、鼻につく匂いがした。
元より、高校時代の僕は、そんな匂いなど気にするわけもなく、注ぎ口付きのポリタンクこそ、山岳部の必需品と信じて疑うことすらなかった。もちろん、匂いはそのまま山旅の記憶になった。
PET 素材やポリカーボネート製の水容器が主流となった現代では、「水容器素材の匂い」など考えられないことなのかもしれないが、当時は匂いはしても「水容器」=「ポリタンク」であったのだ。
そのポリタンクを抱えて、山頂と往復したのが、この「水場」だった・・・。
高校時代の僕は「装備」担当で、山での調理・給食を担当する「食糧:エッセン(なんでドイツ語を使っていたのか、当時も、もちろん今も、よくわからない)」係ではなかったが、それでもみんなのポリタンクを集めて、この水場へ、水汲みに来たことがあったように思う。
それが、山頂まで時間にして 15 分ほどの・・・ ここだった。

水場まで、下りてみたい気持ちがしなかったと言えば、それはウソになる・・・、が。
クマも喉が渇いたら、水を飲むだろうし、もちろん、山の中では水探しも一苦労だろうし、ならば、いつも水にありつけるヒトの水場を覚えて利用することもあるかもだし(実際あるそうです)、そうなると水場は、クマさんと鉢合わせする可能性「大」なりで・・・、とにかく、クマだけには会いたくない・・・
それに今、飲み切れないほど、水、持ってるし・・・

しばし、休憩を兼ねて水場へ続く道を眺め、水場行きは断念。ここは、登頂を優先することに。
時刻は 11 時 48 分、目標に設定した 12 時が迫ってきた。

711米峰を越えてからは、久しぶりの運動に多少は身体が慣れたのか、登り始めほどの苦しさは感じなくなった。それでも、汗水たらす状況に変わりはないが、足はしっかり前に出る。

山頂まであと「5分」の案内石もあった。最初に見た時は、脳が文字の縦横変換に失敗し、「意味不明」であったが、横を通過する際に、意味をようやく理解。
正直、ここから先は、もう、無我夢中・・・
忘れたいことを、全部、忘れて。
なぜ、僕は、ここへ、来たのか?
なぜ、僕は、ここへ来たいと思ったのか?
なぜ、僕は、ここへ、来なければならなかったのか?
いちばん 考えたくない
生きている理由のようなもの すら
忘れて。
はぁ はぁ はぁ
いちばん そらに ちかい ばしょ へ
ぼくは ゆくんだ。
あぁ 40年を経て拝む 薬師如来さま。

薬師如来さまの背後には・・・
変わらない ふるさと の まち が 見えた。

僕は、あまりにも有名な、ある会話を、思い出した。
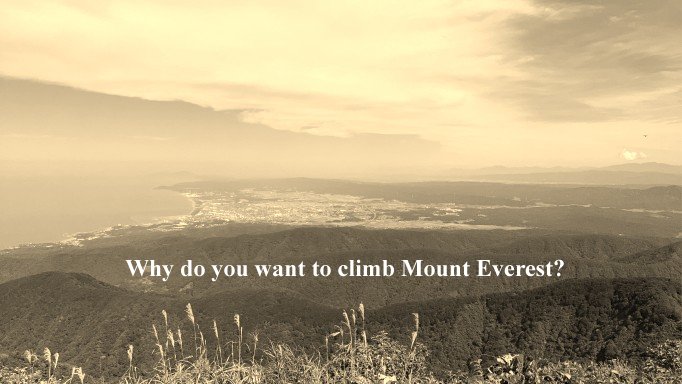
登山家ジョージ・マロリーは、1923年3月18日付の ニューヨーク・タイムズ のインタビューで、記者から発せられたこの問いに対し、次のように答えたという。
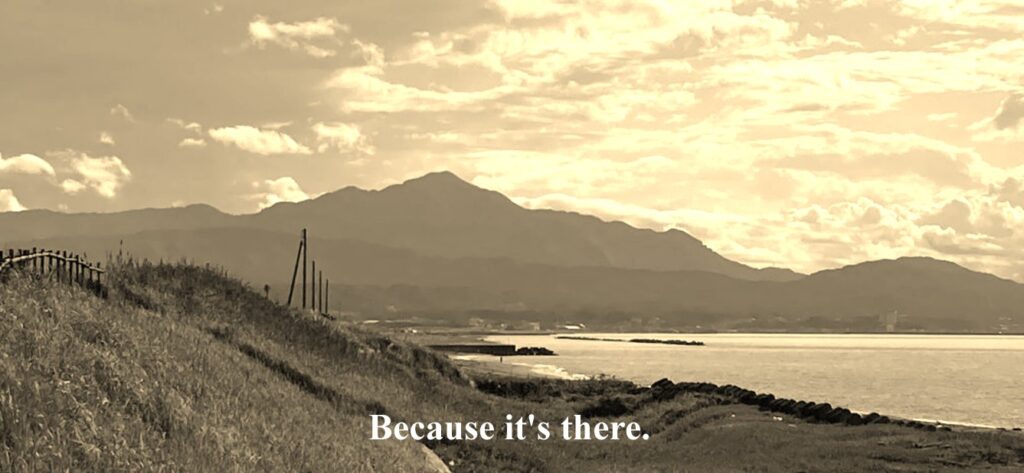
うん。Malloryさん、
僕も こころから そう 思えた。